筑波大学での短腸症候群(Short Bowel Syndrome: SBS)の治療について教えてください
成長に合わせた管理と治療
私は2011年に筑波大学に着任し、今年で6年目になります。現在、当科には他病院で手術をされた方も含めて7名のSBS患者さんがいらっしゃいます。
SBSの原因は、先天性の場合と、手術等で腸切除をしてこの疾患に至った場合があります。先天性のSBS患者さんでは、思春期までは同じ医師が継続診療するのがよいと考えています。しかし、最初の担当医がSBSに関してあまり専門性が高くない場合は、急性期を脱した時点で専門医に紹介し、診療を行うのが望ましいと考えます。SBSに詳しい医師でなくても急性期はある程度乗り越えられますが、その後の臨床経過をみながらの合併症に対する予防的な手段や、そこから先に行う栄養療法、腸を長くする手術、薬物療法などは、対処の仕方によって患者さんの後々のQOLが変わってくるため、専門医が診療することが望ましいと考えます。
当科では、小児期に受診した患者さんを成長段階から成人後まで継続的に診療しています。小児患者さんの場合、成長・発達を常に考慮しなければならないところが、成人の患者さんとの大きな違いです。子どもの成長・発達には個人差がありますから、その子の状態をきちんと把握し、2~3ヵ月ごとにフォローアップをし、治療方針を検討します。腸の状況を改善するために手術を行うのか、どの薬を使うのか、使う時期や期間はどうするかなど、患者さん個人に合った治療法を丁寧に見極めることが重要なポイントです。成人の場合は社会生活におけるQOLを考慮しますが、小児患者さんの場合は成長と発達を常に念頭におき、大人の尺度とは異なる社会環境下でのQOLを考慮する必要があります。
手術のタイミングを見極める
小児SBS患者さんの腸管延長などの手術の施術時期は、患者さんが成長過程にあるため非常に慎重に決定しなくてはなりません。施術時期の決定は、専門とする小児外科医師が担う仕事と考えます。
当科では腸管延長術を多く行っています。腸管延長術には、腸管に互い違いに切れ込みを入れて短冊状にするKimらのSTEP(Serial Transverse Enteroplasty Procedure)と、小腸を縦方向に2つに分けて延長するBianchiらのLILT(Longitudinal Intestinal Lengthening and Tailoring)があります。施術時期は、肝臓の状態や腸の吸収の状態を確認しながら決めていきます。手術のタイミングによっては効果が上がらないことがあるため、見極めが重要です。書籍や論文には多くの施術法などの報告がありますが、実際にやってみないとわからないことも多分にあり、その点がこの領域の難しさといえるでしょう。
SBS治療のポイントについて教えてください
小児SBS治療の考え方
小児SBSの治療では、成長過程を考慮しながら病態を把握し、タイミングに応じた治療戦略をたてることが重要です。外科的治療、内科的治療のどちらか、あるいは両方を選択するかなど、タイミングごとに様々な見極めが求められます。また適切な治療戦略をたてるためには、患者さんをよく診ることが必要です。これらは当たり前のようですが、あえて確然としておくべき重要なポイントです。よく「症例経験数」という言い方をしますが、もともとSBSは症例数自体が少ないので「数」はあまり考えていません。「数」ではなく、どれだけきちんと一人の患者さんに向き合うか、その患者さんに合った治療法を見極められるかが大切なのです。
栄養療法の注意点
SBSの栄養療法は、はじめは中心静脈栄養(Total Parenteral Nutrition:TPN)を中心に行い、最終的にはTPNを離脱し経腸栄養(Enteral Nutrition: EN)へ移行することが目標です。TPN離脱が困難である場合はQOLが高くなることが目標となります。SBSの栄養療法では、肝障害やカテーテル感染(カテーテル関連血流感染症)の頻度が高いので、これらをできるだけ起こさないように管理し、生じた場合には患者さんの状況をどう克服するかが非常に大切です。そのためには、肝障害の発症予防を考慮しながら栄養療法を行うとともに、感染症の発現にも留意しながら、TPNのための静脈アクセスルート温存を図ります。6本の血管のうち腹部より頭側には4本のアクセスルートしかありませんから、そのうち最低2本は温存するようにして、不測の事態に備えておく必要があります。こうしたことを意識しながら治療を行うか否かで、その後の患者さんのQOLも大きく違ってきます。肝機能を維持しながら、いかにENへの移行を考慮するような栄養管理を行うかが大切で、このようなことを踏まえながら、患者さんを成長・発達させていくようにしていくことが栄養管理の鍵となります。
肝障害を起こさない治療
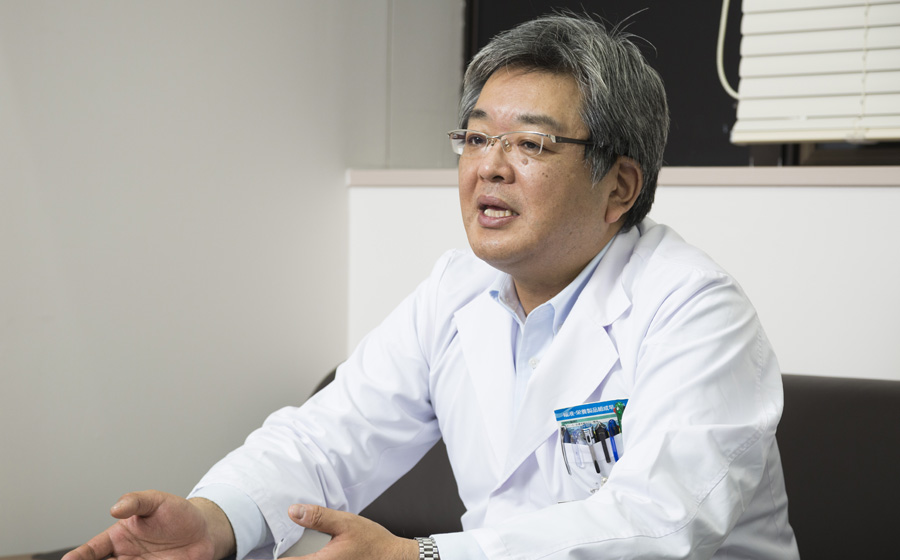
肝障害の発現時期は、術後からある程度腸管が使えるようになるまでの間の急性期に生じる場合と、症状が落ち着いて在宅静脈栄養法(Home Parenteral Nutrition:HPN)に移行できるようになる慢性期に生じる場合の2つに大きく分けられます。
慢性期に入るとTPNの輸液量や成分はほぼ決まってくるので、肝機能に負担が大きい成分で肝障害を起こさないように注意します。TPNでは、無脂肪あるいは低脂肪が続くと脂肪肝になります。また、脂肪を摂取していても十分に吸収されない場合もあり、脂肪の摂取不足による肝障害も多くみられます。さらに、カロリー補充により糖質過剰になって脂肪肝に至る場合もあります。そうした状況をよく把握したうえで、糖質、脂肪、アミノ酸の量を適宜考えながらTPNを実施します。また、少量でもいいのでENを実施することも重要です。
一方で、肝障害には糖質や脂肪に限らず、ビタミンや微量元素の摂取量、腸内細菌叢の変化に起因する問題など、複合的な要素が関わっています。まずリスクを一つひとつ減らし、肝障害やそれに続く肝線維化への移行を食い止めることがポイントになります。肝臓の線維化や炎症がどの程度起こっているかを考え、それ以上進行しないよう、できる限り過不足のない栄養管理を行う工夫が必要です。
小児SBS患者さんにおける採血の難しさ
5歳以下の患者さんでは、検体量を多く採取できないことが問題になります。体格や体重を考えると、少ない採血量に越したことはありませんが、正確なデータを取るためには「絶対必要量」があり、限られた検体量では検査項目を少なくせざるを得ません。それもまた、小児SBS治療の難しさです。
したがって、定期的に採血を行う際は、無理のない採血量を考え、時期や病態に合わせて検査項目を選択します。最小限の検体量で最大限の項目を測定することを念頭に、「一つ上のモニタリング」を提供することが、患者さんにとっていい結果を生むことになります。
臨床検査項目を選択するポイント
小児SBS患者さんの場合、肝障害の進行がないかを定期的に検査します。超音波検査の追加や、AST・ALTといった一般的な検査以外にも、可能であればヒアルロン酸やコラーゲンなどの肝線維化マーカーを測定し、客観的に肝臓の状況をみます。また、肝合成能をみるためにコリンエステラーゼ測定も考慮します。
現在の保険診療では基本的に11項目しか測定できません。一般的なスクリーニングには向いていますが、詳細な検査項目データを必要とする希少疾患の検査としては不十分です。SBSでは基本項目以外の項目も測定しなければ判断できないこともあるので、どうしてもデータが必要な場合は、患者さんや病院の負担で検査することもあります。
HPNでのモニタリング
HPNでは、栄養を過不足なく摂取する必要があるため、定期的なモニタリングが欠かせません。病院にも、最初は週1回、落ち着いた頃でも2週間〜1ヵ月に1回は来院していただいて、状況を確認します。
親御さんには、尿量や便の状態、食事量、体温、嘔吐の有無など、家庭での状況を日誌につけてもらっています。ただ、「子どものために一生懸命やってあげたい」という思いから、熱心に記入しすぎてしまい、負担をかけてしまう場合もありますから、本当に必要なことだけを書いてもらうようにしています。
そして、私たち専門医は、診療の際に日誌の情報をみるだけでなく、経過を見落とさないように「よく診て、よく聞く」ことを心掛け、病態を確実に把握するようにしています。
臨床栄養学の重要性
栄養療法は海外の教科書には数多くの記載がありますが、日本では臨床栄養学に関する講義はほとんど行われておらず、治療として十分に確立されていないのではないかと思っています。日本の医師は、医学教育の中でもう少し臨床栄養学を学ぶべきではないでしょうか。
大学の卒後研修で栄養サポートチーム(Nutrition Support Team:NST)の教育を受けると臨床栄養学に興味を持つ人は多いのですが、学生時代に習っていないので、なかなか馴染めないということもあります。また、臨床栄養学は栄養士の領域だと思っている人も多くいます。しかしながら、栄養療法は基礎的な治療の1つですから、その基礎を理解していないと様々な弊害が出てくるのは必然であり、懸念されるところです。
SBSの治療や管理を行うためには、やはり臨床栄養学を理解していなければいけません。SBSは単純に外科的治療や移植医療で治る病気ではありませんから、臨床栄養学は絶対に必要です。手術だけをされてこられた先生方でも、TPNを始めると臨床栄養学がどれほど大事かということをご理解いただけるかと思います。
筑波大学小児外科におけるチーム医療について教えてください
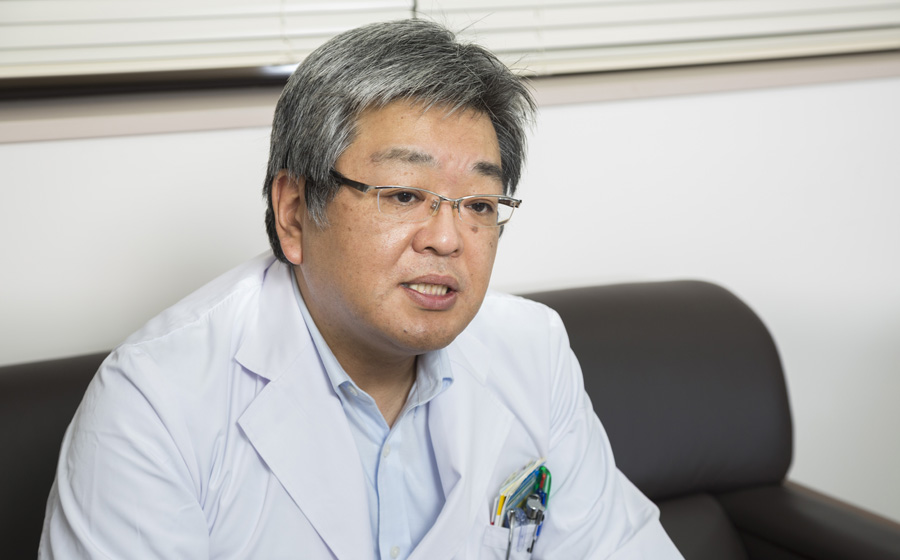
基本的には私がチームの中心になって指導しています。他に、臨床栄養学に興味がある医師や大学院生で研究チームを構成しています。さらに週に1回、管理栄養士への指導もしています。管理栄養士でも、SBSは全く診たことがないという方がほとんどです。
当大学では、管理栄養士とわれわれ小児外科医、消化管を専門にした小児内科医がよく話し合いをします。特にSBSに関することは、小児外科医が中心になって管理栄養士や看護師と検討し、ときどき薬剤師にも入ってもらって治療方針を決めていっています。
私が赴任する前は、当大学には栄養管理や先天性の腸管疾患のことについて詳しい先生があまりおらず、小児SBS診療に慣れていない状況でした。しかし、教育・指導することにより、最近は興味を持つ人が徐々に増えて、とてもいいチームに育ってきていると思っています。
チームで治療を行うメリットは、複数の人の目があるということで、他者の視点からの意見が聞けることです。互いに様々な意見を出し合うことでスキルアップにもつながり、治療戦略が広がることはとても大事なことだと思います。
ただ、まだ完全なチーム医療とは言い切れないのが現状です。今は私が中心になっていますが、将来的には栄養管理のスペシャリストが育ち、対等に意見が言い合えるようなチームに成長させたいと思っています。
初診で来られるSBS患者さん・ご家族とのコミュニケーション
現在、当科ではセカンドオピニオンの形は取らず、在宅栄養外来という形式で初診でも受診しやすいようにしています。患者さんやご家族は困っていることがあるわけですから、受診しやすいようにし、まず話を聞きます。SBSのような複雑な疾患においては、血液や画像などの臨床データが何もない状態では、適切にお答えすることができないこともあるので、その後に関係の部署や病院でのより詳しい経過などを照会させていただくようにしています。
せっかく来ていただいた患者さんやご家族に少ない情報で安易にお答えすると、誤った回答をしたり、患者さんと主治医との関係を壊すことにもなりかねません。ですから、まず受診していただき、問題点をお聞きした後、できるだけ情報を得て、その後にどうするべきかをお話するのが一番いいと思っています。
SBS治療にあたっての問題提起
SBSのような希少疾患の場合、患者さんを診る機会はそう多くありません。SBSの治療は経験が重要で、専門医が関わる必要がありながらも、実際には経験を積む機会は少ないのが現状です。
私は、SBSを専門にしている施設に患者さんを集積するとよいのではないかと考えています。日本は「自分の施設で診る」という考え方が主流で、それが国内における希少疾患治療の最大の問題点かもしれません。患者さんをいくつかの専門性が高いセンターとなる施設に集めることで、包括的な治療も行うことができ、良い結果を生むと思います。初診の段階ですぐに送っていただいてもいいし、ある程度経過してから送っていただいても構いません。送るだけではなく、患者さんのQOLを高めることを考え、一緒に治療していく形でもいいと思います。何よりも、患者さんに対して専門的治療を行うことが、希少疾患の治療において重要だと考えます。
今後のSBS治療について教えてください
SBS治療の目標は、可能な限り短期間でTPNから離脱することです。そのためには、腸管順応を改善すること、肝障害などの合併症を予防・治療でき、血管温存しながらアクセスルートを確保することなどに留意することが大切です。その一助となる新しい薬剤などにも大きな期待をしています。
加えて、TPN施行中に生じるカテーテル関連血流感染症を予防できるデバイスや、肝障害を起こしにくいような栄養剤の開発が待たれます。





